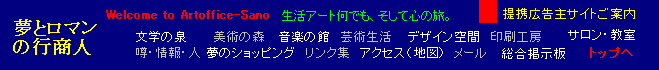
|
||||||||||||||||||||||||
| ★このサイトはwindowsのみに対応しています。他のOSでの画像の崩れなどご了承ください。表示→文字のサイズ→(中)でご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||
|
「風のように」14−03−13 |
||||||||||||||||||||||||
|
鳥が二羽、はばたいていった。セキレイか。大根の畑が広がっている。都心の郊外もまだ 自然が残っているものだと、今更ながら思う。きっとつがいの鳥だろう。餌を探しながらでも後 を追いかけて飛び交っているセキレイ。恋人同士か、夫婦だ。白髪混じりの長めの髪の毛を 、男は指でなでる。 昨日お茶飲み友の女性に「今日限りね」と意味不明のことをいわれた。なぜか分からなかっ た。鳥も、猫も、犬も、男も女も優しさのあるものみんな恋人にしてきたつもりだった。何人の 恋心を知っただろう、とつぶやいたのがいけなかったのか。 一つの傲慢さが相手のひんしゅくをかったことに違いはない。もうどうでも良かった。すれ違 いのすきま風は付き物だ。又新しく何かとの出会いがあるだろう。男はまだ飛び交い合ってい るつがいのセキレイを眺めながら歩き始めた。 縁があれば形はどうあれつづく。夫婦のように。恋にのめり込む年ではなかった。お互いい やなことはさければいい。それがすべて何事も無事に行く基本だ。 「さて積極的に活動できるのは後何年だろう」 そうつぶやくと、若者気取りで男は足早に目的地へと向かった。 目的地、それは畑を通り過ぎたところにある杉林の中である。その先はすでに高層のマン ションが建ち並んで久しい。花粉症が叫ばれてからというもの、その場所は閑散としている。 「いらっしゃいませ、ようこそ」 一日おきに来たときも、すでに10年もの間、老婆は同じ事を言った。そして同じものを毎回 注文するのを知っているのに、 「どれにしますか?」と、必ず聞いた。 男はいつものカプセルと飲み物を頼むと、専用の部屋の鍵をもって細い廊下を通り抜ける。 その過程で赤い粉の入ったカプセルを飲み込む。10分もすれば効いてくる。部屋の中はい つもと同じだ。「忘れる部屋」と入り口にかかれている。その日はそこだった。 楽しかった昨日までの「恋人」との日々を忘れる。忘れることは更地にしてほかの家を建て ること。すなわち廃墟が創造の原点となる。 赤い粉は胃袋にはいる。微粒子がまるでウィルスのように手足を伸ばし瞬く間に拡大してい く。その連続の動画はエクスタシーの継続といったらいい。目をつぶったまま男はその快感を 味合う。 快感は何も感じないことだろうか。たとえば忘れること。記憶という語句がなくなること。男は リクライニングのいすであたかも昏睡状態だった。窓から見える杉木立は水面に映る影のよ うで、窓辺の鳥達は模造品だが何かの歌を歌っている。 好きこのんで忘れたい訳ではなかった。思い出も人生の酒肴品になる。それすら削除した いという欲望。何かが狂い始めていた。 模造品の鳥達はモーツアルトの2楽章を奏でている。ゆったりと何時間もの時が流れていく ようだった。 「お時間です」 それといっしょに熱いコーヒーが運ばれてきた。大工さんのような老女の手から、何かが部 屋一面に充満していく。 「ありがとう」 男はつぶやくとふっとため息をもらす。ドアのしめる音が「お疲れさま」といっているような気 がした。(おわり/ed ) |
||||||||||||||||||||||||
|
「酉の市」14−11-19 |
||||||||||||||||||||||||
|
曇天。似合うのはカラスだけだ。3羽の黒い浮遊物がけやきの枝葉の間から見え隠れして いた。まだ例年よりも早い時刻だったためか混雑というほどでもなかった。たこ焼や焼そばな どの露店が仕込みを兼ねた準備で忙しい。もちろんカラスは彼らの残り物がねらいだろう。 神社の境内は曇り空に反映してか、なんとなく重たい。いっそのこと早く日が暮れればいい のに、と男は思う。早く暮れればそれだけ仕事も速いし・・・。 かみそり、カッターナイフ、薬をしみこませたタオルもある。男はそれらを再確認した。・・・・ ある。手に触れただけで恍惚となった。かって失敗はなかったのだ。 精神と肉体とを一切のわだかまりから切り離してくれるかみそり。カッターナイフは強引な境 界線を作ってくれる、いわば希望が残る離別手段にもってこいだ。もちろん化学薬品は欲望 をかなえてくれる略奪完全犯罪の助っ人。 はち切れそうな細身のスラックスをはいた女将さんが仲間の女達とけたたましく笑いながら 境内に入っていった。大枚はたいて熊手を買うのか。ぷりぷりした腰を武器に値切ればいい 。きっと安くしてもらえるだろう。でもそうはいかない。その前に・・・。 ぞろぞろと人が集まってきた。そんな頃合いだ。よりどりみどりで今度は子供がいい。焼き そばをねだっている小学生。母親には興味ないが利発そうな男の子。きっと自分も昔はあん なだったはずだ、と男は思う。優等生だった。先生にこびを売ってひいきされてもいた。それ がどうだ今は。熊手の御利益を期待した、一介の自営業者に成り下がった。あとは人生に決 断を下すだけだ。お供のターゲットと一緒に。 この酉の市に場違いな娘がいた。携帯電話をかけている。きっと彼氏と待ち合わせかもし れない。お台場で躍りでもするのかといったコスチューム。彼がやってくる前に欲望をかなえ るのだ。男は薬の染みたタオルを握りしめた。かなえるために欲望はある。 去年と同じように、男はまず、用意しておいた缶ビールを空ける。普段はのまない。毎年こ の酉の市でのむだけだった。そしていつもの裏庭に行く。誰もいない裏庭。すっかり日も暮れ てきた。計画を実行する時刻だ。 350ミリリットルの最後の一口をのむ。毎年のように暗闇が霞掛かってみえてきた。眠気が 理性を覆い被せる。カラスはもういない。餌にありつけたのか。それとも明日の朝に持ち越す のか。 しばらく時が経った。男はなんと一人づつ獲物をとらえていった。精神と肉体とを切り離すか みそりは女の尻から、真っ赤な血をはじき出した。「きゃー」。鮮血と叫び声は優柔不断の男 の日常を一気に変えるようにほとばしっていった。 間髪を入れずにねらっていた子供は肩から腕にかけてカッターナイフが走った。昔の思い 出や曖昧な希望から切り離すように、でもまだ未練があるのだといわんばかりに男は子供の やわらかな筋肉に深い傷を作っていた。子供の目は「ごめんなさい、助けて!」とつぶやいて いた。そして最後にもっていたタオルでお台場娘の顔を覆った。あっという間に無言のまま娘 は男になだれ込んできた。と同時にそのタオルで自分の顔も拭った。キンカンの染みたタオ ルは、男の体中に染み渡るように男をひとときの眠りから神社の裏庭にまで引き戻していた のだった。眠っていたのだ。 「恒例の、自我覚醒はカラスのように、明日までは持ち越せないのだ。これでこれからも商売 繁盛だ」 男はそうつぶやいて、にやりとした。 (おわり) |
||||||||||||||||||||||||
|
「時計」14−12-07 |
||||||||||||||||||||||||
|
時を刻んでいる。宇宙の流れのように人が作った機械が動いている。確実に明日は来る、 確実に時間は無限に進む。一切のわだかまりを無視して、ガン細胞が繁殖するようにそれ は確実であった。 コチコチと空気を1秒づつ遮断していた。空に音を刻む。それは切断そのものだった。なん とむごい音を人は作り出したのだろう。細胞の一つ一つをはぎ取って行くかのようだ。時計は 細胞の寿命を知らせる役割をもっているのかもしれない。生まれたての赤子の細胞もマイナ スから刻まれているのだろうか。 女はいきなりコチコチとなっている鏡の横におかれていた時計をつかんだ。 「おいしそう!」 ピンクのプラスチックに覆われた手のひらサイズの置き時計。瞬く間に女の強靱な歯によっ て破壊されていった。 「うわさ話を食べているみたい。愚かな恋愛の記憶もかみ砕いている。 おいしい他人の不幸ごと。横取りされた恋心。みんなこんな味がするのね」 時を食べ尽くす女。50年あまりの間なぜ気がつかなかったのかしら、こんな快感。女はつ ぶやきながら最後の秒針を飲み干す。そして、 「明日からまたおいしい出来事が待っているかもしれない・・・。人の不幸よ。たまらなくおいし い他人の噂」と、いいながら、ティッシュペーパーを取り出し、口元を拭く。紅に混ざり合った 血の色がどす黒く跡を残した。 「お茶でも飲んで、発声レッスンなどして・・・」 キッチンにかけてある壁掛け時計は、夜10時10分を指していた。もちろん何事もなかった ようにコチコチと空を刻んでいた。まるで、無味乾燥なタンゴの 四拍子のように。(15/02/09) |
||||||||||||||||||||||||
|
「振り向いただけ」15−02-14 |
||||||||||||||||||||||||
|
コーヒーがいつもと違って苦い。銘柄の違いではない。沸かし過ぎか、粉の分量の間違いだ 。でもクレームを出すのはやめよう。なにもおいしい物を求めに日参しているわけではない。 女は努めて明るくいった。 「ここは息抜きに一番いいところ。いつも悪いわね、コーヒー1杯で何時間も」 「とんでもない。いいんですよ何時間でも。何なら一日中でも」 マスターはいつものように無表情で受ける。女は見抜いていた、この男はふぬけの典型だ と。 「あたしの亭主とアトモスフィアが一緒なの。すてきよマスター、いつみても」 「おっと、のろけてるのか、ほめられてるか・・・微妙ってやつかな」 いっぱしに男としての反応はできる。でも夫とは本質的に違う。雰囲気など、今更興味はな いが女は日々の夫との再確認にきているのかもしれない、と自覚していた。 カウンターと2,3のテーブルがあるだけの小さな喫茶店。有線放送が唯一格調を保ってい るみたいだ。 「あたしクラシック音楽は好きじゃないけど、ここのBGMは気にならない、むしろマッチしてる は、あなたマスターと」 「なんだかケーキでも出さないといけないみたいだな」 いつものプロローグだ。女は夫にいえない日常があった。 ふぬけの男性になぜかあこがれる。お客の幸も不幸もの、ことがらを餌にして太り続けると いった、夫にはない、飛び交う蠅の習性。いつ自分が餌になるかを知っていてもその前に自 分の物にすればいいし・・・。 そんな男に限って、肉欲的な満足を与える力は人一倍にあるのだ。そう思うだけで、夫を一 瞬でも忘れられる。 「今度ドライブでもしない?こっそりと二人だけで」 「ん?・・・いいんですかこの僕と二人だけでなどと」 淫靡な笑みを浮かべる男。そんなときに限って、頼まれ仕事の日々に活気がみなぎる。 「あら、目が輝いている。ほほほ・・」 女はたばこを取り出すと火をつけ、その日初めての、そうだ深呼吸だった。 「うまそうにすうんですね・・・。そろそろ体のこと考える歳でしょ?」 「夫がここへ来ることないけど、内緒よ、うちの娘にも」 さらに女は続ける。 「大手製薬会社の健康食品部門を立ち上げた夫。失敗したらくび覚悟で・・・。大変よ、もう。 今は軌道に乗ってるけど、あたしが有害趣好品愛好者だと知ったら離婚!」 笑いながら、と りあえず深刻ぶる。 「それは大変だ。ドライブには、どうぞ何箱でもたばこを持って」 「あらいやだ。立て続けになんか、喫煙だめなんてできない」 「じゃドライブは他の目的で・・・」 「そうよね。それは任せるは、どうにデモして!」 マスターはそれを聞くと、驚く早さで、カウンターの下から手帳を取り出す。 「日にち?・・・やだ、ただ振り向いてみただけよ!自分の足跡にね」 足跡?男、マスターはきょとんとした後、意味不明の言葉をわかったような振りして、うなず く。薄汚れた手帳の表紙がカウンターの照明を鈍く反射させていた。(おわり)15−03−16 |
||||||||||||||||||||||||
|
「車の中で、二人きり」15−05-11 |
||||||||||||||||||||||||
|
緑の中を走り抜けてく、真っ赤なポルシェ・・・そんな流行歌があった。 「海を見に行く?それとも紅葉の山?」 「山がいいかな・・・。任せる、どちらでも」 彼女は運転しているにもかかわらず男にすべてを任せている風情。 「あたしはこのポルシェで走れればいいのどこでも。じゃあ山にしよう」 昨日納車になったばかりの赤いポルシェだ。1ヶ月ほど待っただろうか。それだけに思い は強い。 「初めての新車に俺を乗せてくれるなんて・・・」 男はそれだけでうれしかった。 「いいのよ、思いつくのが君しかいなかったから、ただそれだけ。それに久しぶりだね、会う のも」 秋口。都会でも各家々は紅葉。でも決してきれいではない。二人はしばらくポルシェの乗り 心地を体で感じていた。静かな騒音。沈黙。 「君。知人、友人、愛人の定義いえる?」 唐突に彼女は口を開いた。 「・・・・」 男は彼女の顔を見つめた。答えがでない。 「東大受験した自信があるのに理論派じゃないんだね、君」 彼女は一気に話し始めた。 「知人は単なる知り合い。相手が困ろうとなにしようと無関心。利用できればおつきあいした いってところ。友人は、相手の境遇の変化に関係なくそばにいて見届けてくれる。意見も言 ってね。愛人は、そこにセックスがつく。その究極が夫婦ってとこかな。アメリカにこんなこと わざがあったわ。君も知ってると思うけど、『Fine weather friend』。雨になったらおつきあいできないわっ、て人かな。だからあたしは愛人をたくさん作 ろうかなって思うの。君に初めて奪われたときからづっとそんなこと考えていた。単なる知人 を友人と勘違いしていた時期もあったし、知人を愛人にさせようと大それたことを考えていた ときもあった。みんな間違え。だってタイプがあるでしょ。仕方ないよね、だからちまたで失恋 だなんてことがあるのよ。みんな勘違い。片思いが最高の恋なんて哲学者もいたけど、それ は別として、今の世の中、本物しか生存できないとあたしは思うの。だったら本物は愛人し かいないんじゃない?そんなことも話そうと思って、今日誘ったのよ君を。あたしを利用しよ うとして、君との関係以来あたし、何人も知人と関係を持った。持ちたかったのもいる、男も 女も沢山。でもみんなだめ、又はいわゆる失恋。みんなあたしが資産家のお嬢さんだからと 寄ってきただけだった。宮内庁関係もいたわ、君も遠いけどその一人かな。うん、でもやっ ぱり君はあたしにとって少し違う、初めてだったってこともあるだろうけど、あたしと同じ独り 身。39歳にもなって!時々くれたどうでもいい、君の手紙、和歌、それがあたしを縛ってい たのよ。・・・・本物の関係は、そうセックスというオプションのついた友人だわ。どう思う?あ たしの解析」 一気に話し終えると彼女はドボルザーク「新世界」のCDをかけ始めた。車の騒音が嘘のよ うに消え、その交響曲が鳴り響く。それも高級車の嘘のような価値なのか。 「一切の車のエンジン音が消えたみたいだね。すばらしい音響だ、車の中だというのに・・・・ 。未だにこの曲、気に入ってるの?」 指揮者は誰とか、男は少々うろたえ気味であった。和歌でしか気持ちを伝えられなかった のだろう、彼にふさわしい挙措に違いない。 彼女はマニュアル仕様のギヤを左手でオートに変え、その白いしなやかな指を男の太股 に滑らし始めていた。 「御免ね、あたしが何の反応もしなかった。あたしの作った君への和歌だってたくさんあるの 。君がもっと積極的だったら。でもそんなこと今の時代関係ないわ。あたしは本当の愛人を 作るのだから・・・。」 男は、すでに高速道路に入った状況で、指を指した。その顔はすでに初めて彼女との夜の 男の顔になっていた。 「・・・・それから、紅葉見物をしようか」 まるでクレヨンで書き殴ったような山の色。赤、橙、黄色、それに少し汚れた茶色。どの森 も林も山も森もみんな秋そのものであった。 彼らは2回目の逢瀬に燃え尽きていく。男は我慢し尽くしていた情熱を、女は達観した火 のような氷をその部屋に充満させていた。 駐車場に残され、ナンバーを隠された真っ赤なポルシェ。明日は誰が助手席に乗るのか な?男?女?知人?友人?愛人?そんなことを考えていたとしたら・・・・。でもポルシェは思 ったかどうか。 「もうすぐ凍てつく冬だから」。 (終わり)15/11/2 |
||||||||||||||||||||||||
| 「暖冬」16−12−20 | ||||||||||||||||||||||||
|
年々冬が消えていくようだ。均一化する気候、そして人間の個性。時の流れで片づけるしか 手だてはない。 男はマフラーを巻き直した。暖かいといっても、やはり気分的に冬、いや心情的に冬であっ てほしい。安物のスーツと同じくらいの価格のマフラーだった。女房に食いつかれた、いわくあ りの銀色マフラー、特にすきだった。3万円ものマフラーなど買うほどの経済状態ではなかっ た。家のローンも大変だったというのに。 若い頃から男は流行を重ね着するのがいやだった。はやりものは風邪だけでいい。 山頭火の行乞(ぎょうこつ)ものの文庫本を読み終えたばかりの男は、「のぼりつくして、石 仏」・・・自分もそんな心境かと苦笑いする。やくざ映画を見れば、ひととき高倉健になった気 分、そんなたぐいと分かっていても、冬ではない寒さ、いや暖かさに自分だけの世紀末を大げ さだが、感ずる。 登り尽くして見えるもの、辺り一面の町並み。そこでなるほど放尿もいいだろう。達観の錯覚 ともいえるか。錯覚の連続が人生ならばそれもいいだろう。なにをやっても自分は自分にか わりはない。 小旅行だった。単に足腰を鍛えるためにのみ3キロの道のりを歩く。毎日。健康のためだと いう。石仏をみる心境が、なぜ健康?家族がいるから・・・?。どうでもいいさ、生きて行くには 支障がない方が。 「まだ生きていてほしいのよ、元気で丈夫で。無駄遣い癖のあなたでもね!」 いつも強がりの女房の言葉だった。一つの愛情と受け止めていた。 銀色マフラーを巻き直すと、男は「いつもと違うコースを歩くとするか」とつぶやく・・・・。枯れ 葉もすでに汚い色合いで散らばっていた。時折とおる車の排気ガスと一緒に小さな渦が巻き 、風流さなどみじんもないゴミのような枯れ葉が舞う。 妻との約束事を破るわけにはいかなかった。たったの3キロでいいから、しかも天気のいい ときだけでもいいの。分かったと妻に言っただけで、以来男は実行していた。 高台の地点。自分の家も望める。確か今の家は業者がなにを思ったかここに連れて来て契 約したようだった。もちろん妻のたっての希望もあったが。 息子夫婦が、あの小さな家を管理している。何のもめ事もないが、代を譲ることはやはり寂 しい。 「あなたのばかばかしい浪費がなければ、子供に譲ることもなっかたのよ、それをねらってい たところもあるけどね、あの子は」 笑いながら言っていたが、浪費はマフラーだけではない。もちろん身につけるものほとんど が妻に言わせれば無駄だったろう。妻や子供達はスーパー専門だった。下着も靴下も。ハン カチまで男は自分で調達していた。 男は何のグループだったか、その中で間抜けな「ベストドレッサー」に毎年選ばれるのも楽し みにしていたくらいだった。 「何の趣味もない、いいだろうそのくらい」 高台の小さな空間。妻と一緒に来たのは2年前だったか。空を見上げた男は、カラスを確 認して、また自分の家を眺めた。自分が立っているところから2メートルも離れていない、ふと 目に止まったもの。何度か来ていたが一度もみたことのない高さ20センチほどの地蔵さんだ った。 「石仏?」 そういえば冬枯れの時期には来たことのなかった高台だった。雑草に隠れていたのか。 山頭火を思い出すのと同時に、男は病床についていた妻の笑いながら言ったことを思い出 していた。 「もう一度あの高台に行ってみたかったな」 そこには、今、石仏がたたずんでいるばかりだった。男は、去年病床についたまま逝った妻 の面影をその石像にみる。そして、風に揺れた銀色マフラーが男の涙腺をくすぐる。(了) 16/12/31 |
||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||