
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★このサイトはwindowsのみに対応しています。他のOSでの画像の崩れなどご了承ください。表示→文字のサイズ→(中)でご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板にご感想を。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブログ!文芸雑話です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エドワード佐野/佐野義也「掌編小説集」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■エドワード佐野/佐野義也プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●このページの小説↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■恋のオーラ(30・11・02)■碧空(25・9・18)■「余生充実?」(25・9・13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バックナンバー↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
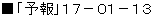
|
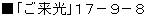
|
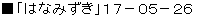
|
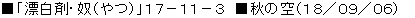
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
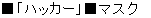
|
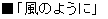
|
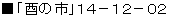
|
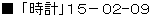
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■恋のオーラ(30・11・02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この掌編は第14回(4000字)短編恋愛小説「深大寺恋物語」公募に応募し、フォーマットに合致できなくて、再送信も認められなかったようで 入口で一切読まれずに落選したものです。ポスターまで大々的に出し募集しておいて、再送信のものは失格というのも腑に落ちませんが、才能なしとあきらめています。どうぞ御笑覧くださいませ。 カラスのつがいらしき二羽が男の視界に入る。曇り空にはよく似合う鳥だとつくづく思う。薄紫色したアジサイの群落を、フェンス越しに眺めた後、参道を歩く。バスが異様に大きな排気音を立てて 男の横を通り過ぎた。以前なら「無粋者めが」と、呟くのだが、今は黙って流れに譲る。これから久しぶりの敬虔な時を持とうとする七十二歳の男だった。 地元 にいて四十年以上にもなるのに、この日何度目かの深大寺山門をくぐるのだ。今更、元三大師に何を祈願するのだろう。高齢者の新しい恋の成就を願うのか二羽のカラスのように。 いや霊験あらたか天台宗深大寺に祀られている良源こと元三大師様に新しい日々生活の報告を兼ね、先に亡くなった者たちへのレクイエムが目的だった。 長年愛した伴侶を三年前 に亡くし、既に男の親兄弟はすべて他界していた。 今はご多分に漏れず、住まいのない一人暮らしで一年ほどたつ。目の中に入れて育ててきた一人息子は社会人になったいま海外で活動。 出来の良い子供を生んでくれた妻に感謝だったが、そんな子に負担はかけられまい。だから人生謳歌の後生楽、悠々自適、開き直りのホームレスを選択したのだ。 早朝の日課である自動販売機周辺を回り、取り忘れの釣り銭を物色した後、地域一帯古着ゴミ出し日の仕事。まだまだ着られる服を選んでいたところを巡回の警官に尋問されライターを持っていただけで 昨今頻発していた放火の犯人と疑られ、昼までかかって取り調べされていたのだった。 梅雨空、梅雨寒という嫌いな言葉を自分の肌から払拭しながら深大 寺小学校前の交番から神代植物公園入口沿いを通り、ここまで来たのである。青筋アゲハが一匹アジサイの上に舞い、花に彩りを添えていた。 「誰彼構わず自分の汚点を披歴するな、恥を隠し通すのも人生だ。少しは見栄を張れ、君には自尊心がない。それは個性ではない無恥だ」と言いながらも、自分史を書いてくれと、会社員だったころの 先輩から広告業を自営していた男に依頼があったのだ。 見栄を張れとか直截的な意見をくれる先輩上司は自分にはない出世頭の見本だったろう。親しかった先輩後 輩の仲、取材を兼ねて自宅に誘う。翌日は植物公園の散策の後、参道の蕎麦屋にて会食をしながら話を聞く。何度か重ねるうちに、親しみ以上の間柄に…。 取材の中身も彼は自分の貧困時のことはひたすら 隠していたい、自分とは違い誇り高い先輩だった。余生も終わるころだと言いながら、六本木の高級マンションに自宅兼事務所を購入したことなどの成功譚を、 男は聞き取り、念願の遺書代わりの本の代筆をしたのだ。 彼の言葉を裏付ける様に出版社の編集者にも言われたことは「この文章はプライドのない方が書いたものですね」だった。 意味が分からなかったが、ほかの仕事先でも言われたのは「つまらないミスは自尊心、誇りが許さないはずですよ」とはスーパーの販促チラシ作成のレイアウト担当者だった。 自営の広告業だったころの男は、その自分史出版後、高齢で先輩が逝ってしまったころから、その上司の指摘通りいい加減な仕事ぶりや生き方が気になって、それがプライドのなさなのかと朧気ながらも 自覚するようになったのだった。勿論開き直りも目覚めていた。 自尊心、プライドが何の役に立つ、なくても生きていける、ない方がいい。 深大寺参道入口付近にあった園芸店経営の喫茶室で、何年間だったろうか、「モーツアルトの夜」と題して、道楽の室内楽演奏を何人かで毎週やっていた。 何のコンセプトもなく、プライドとか誇りの抜け落ちていた男は、今度は参道にある貸画廊にて「ブナ林その四季」と銘打って油絵個展をやりだした。 妻も受付に借り出してやったものの、大した評判も取れ なかった。 仕事そっちのけであちこちのブナ林写生旅行を気ままに一人で行ったことなども含めて「好きなことばかりやって、商売の広告業はどうするの」、などとたしなめられた妻の言葉も、 横に置いてさて次は何をしよう………。 果たして自営業は倒産した。借金三昧の末、心労で、愛する妻はふろ場で、ヒートショック現象による脳出血で死亡。いい加減な性 格で見栄など微塵もない男を残して。日常から逃れられるといった安堵の穏やかな妻の表情は今でも男は忘れない。 葬儀の時、男は会葬者へのろくな挨拶もできないで泣くばかり、 うろたえている親の挨拶文言の後を引き続いて冷静を繕ってくれていた息子に代弁してもらったのを覚えている。 そして「モーツアルトの夜」での以前から男の知り合いの女性ピアノ弾き。小淵沢から、謝礼はせいぜい深大寺蕎麦の接待だけで、高速道路を駆って調布インターまで毎週来てくれた、 妻にはない音楽の感性豊かなピアニスト。何年かデュオを続けてくれた後、しばらく交流が途絶えたのちに、何が原因か、自殺したとの連絡が入った。 自分のどんなへたくそなフルート演奏 にも、毎回快く伴奏をこなしてくれたピアニスト、小淵沢の小海線が見える歩道橋の上から飛び降りたのだった。家庭や本人に何があったのか、自分とも関わっていたのかと思うと、 男は連絡をくれた娘さんの声を聴きながら嗚咽して悔やみの言葉すら出て来なかった。 妻、ピアニストとも同じように男は二人を愛していた。 また建築家で学生時代からの親友。初詣に、深大寺参詣に案内したことがあった。「モーツアルトの夜」にも顔を出してくれたり、個展「ブナ林その四季」にも来てくれたりの友だった。 その友人も、妻やピアニスト同様に愛した男だった。数年後、彼はパーキンソン病と診断され間もなく亡くなった。 パーキンソンになったと知った友人へのお見舞いの時、「スポーツマン だったお前が、こんな姿になるとは…。もうこれを最後に、見舞いに来られない。お前の悲しい姿をこれ以上見るのが、辛くて」と男は言いながら、友人の手を強く握り、熱く抱擁し慟哭を 残して部屋を後にしたのだった。 見栄を張れと指摘してくれた上司も、アスリートの親友も、ピアニストも、そして妻もなぜか自分と深大寺を背景にかかわって逝ってしまったのは事実だった。深大寺境内一隅に祀られている 元三大師お堂の入口付近、なんじゃもんじゃ大樹の木陰で地元の合唱団とともに男は、フルート演奏をさせてもらったこともあった。その時の演奏は、なぜか大師堂にも響き渡るよう 意識していたのを思い出す。 以来男は妻を亡くしたころからその大師、座主を身近に感じ始めていたのだった。少なくとも普通以上に愛していた他者を、自分から次々と引きはがされていくつらさ。 思い出すたびに男は、めぐりあわせを恨み、これも自分の自尊心のなさからくるのかと、不甲斐ない日々の悔恨に苛まされていたのだった。 参道近辺にはよく出没していたが、深大寺山門をくぐったことが数えるほどしかなかったのをふと思い出す。なんじゃもんじゃ大樹の木陰での演奏くらいで挨拶もなくこの不届き者とは、 良源様も言わないだろうと、軽んじていたことを男は恥じたりもしたのだった。 南門から入ると水車が、ザブン、ゴツンと音を立てている。いつだか初詣に来た時利用した蕎麦屋さんの入口だ。前景は亀島弁財天池、中の島には晴れてもいないのに亀が甲羅干し。 その静寂を壊すように突然青大将が飛沫を残して泳いでいった。獲物の蛙を追いかけている。 「こら、こんなところで殺生はやめろ」と男はつぶやいて山門へと向かった。梅雨時の平日だった。 人もまばらで、恨み辛みをいうのではなく、愛する者たちを昇天させてくれたお礼参りにはもってこいの日和に違いなかった。 お礼参り、なんという自分らしい言葉、と男は複雑だがそんな 気持ちになっていた。自分だけがさみしい思いをするだけで、皆が幸せになれたのだと思えばいい。今自分もストレスのない、プライドも見栄も必要のない日が送れる、皆の分も時間はたっぷりある、 寂しいが死ぬまで。 本堂に手を合わせた後、緑葉茂るなんじゃもんじゃ大樹を横目に、元三太師堂へ登っていく。誰がいようと呟いてお参りすればいい。しかし誰もいなかった。静謐とはこんなことを言うに 違いないと思いながら、男は担いでいた世帯道具一式の入ったリュックを下ろし、少し微笑んで手を合わせるのだった。やや大きめな声で「ありがとう」。 すると突然、ぼろぼろと大粒の涙が頬を伝わって きた。暗灰色の空から水滴が落ちてきたかのように。 男を揶揄するのか、先ほどの二羽のカラスがお堂の屋根の上でわめいていた。男は流れる涙を抑えきれずに、布切れを取り出して、顔一面拭うのだった。「余生幾ばくも無い自分でも、 今まで通り老若男女まだ人を好きになる。だがまた一人残されて辛い思いをするのか」そう思った瞬間だった。 良源の活動した平安時代へタイムスリップするように、導師の全貌が頭の中を 駆け巡ってくるのだった。 先輩上司や同級生の友人、そして小淵沢のピアニスト。何より四十年も連れ添い、よき子を生んでくれた妻。自分が愛した、それら他者の面影、挙措、笑み、すべてが良源和尚と一つになって 男の小宇宙の中で、輝いているのだった。 「そうだ、自分はこれから、元三大師と親しくなればいい。みんなを愛したように座主を恋人にすればいい。不謹慎な片思いでも、立派な恋だ。 自分と同じ ように花鳥風月老若男女誰をも愛せる導師が見放す訳がない」あの凛々しい相貌、まさに抱擁する為にある厚く逞しい胸板。先輩上司や親友にきっと瓜二つ、自分がタイプの最後の恋人だ。 これでもう死後も独り残されることはない。欣喜雀躍、男は更にそう呟いて天を仰いだ。 いつの間にか暗雲が裂け、一筋の日差しがお堂の斜め端から差し込んでいたのだった。誇りや自尊心と無縁の男にも注がれる光背、それは恋のオーラに違いなかった。<了> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■碧空(25・9・18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
隣の県で竜巻被害があった。秋風を感ずるこの頃なのにもくもくと積乱雲が碧空にそびえている。気象状況が極端に変わってきている。オゾ ン層破壊の故だとか、ミニ氷河期の始まりだとかいう者もいる。 今まで砂漠の現象かと思っていたのが都会にも押し寄せてくる恐怖。地球は生きているとは周知の事実だ。異常気象は生き物の営みすべて を無視する現象といっていい。 少年は空を見上げた。いつもと変わらぬブルーだ。深い空とはこんな色を言うのだろう、しみじみと眺めてみた。 なぜ空はブルーというはっきりした色なのだろう。湖や海はその反映とわかるが、空はなぜ?学校の先生もはっきりした答えはくれなかった。 こんなきれいな空が真っ黒な竜巻を生む。 気象予報が少年の毎日の関心事になっていた。その日の天気予報は必ず確認した。ひと時は良く当たると安心していた気象予報、今は当た らなくなっているのが興味の一つとなっていた。 ある冒険家の本で、目が覚めたら生き物が全くいないシーンに主人公が置かれている、という内容のものを読んだことがあった。不気味だっ たのを覚えている。まず、緑がなかった。川に水は流れていたが奇妙にも川底もしっかりと見えるほど澄み渡っていた。生き物がいないために 水も汚れないのだ。まるで生き物はその主人公だけという設定だった。 異常気象がもたらした状況だったのかは忘れたが、少年は碧空と竜巻に、そしてそんな物語を重ね合わせると何かの前兆を感ずるのだった 。 その日も快晴だが、そろそろ急ぎ足で学校へと向かわねばならない。いま学校はスマホとラインといじめの代名詞みたいだった。 晴れていても、少年は気象関係に関心があるだけ、合羽を忘れてはいなかった。下校時には天気がどう変わるかわからなかった。積乱雲は真 夏のものなのに、今は春先、すっかり少年は天気対策を自分流に考えるようになっていた。 教室に入ると、「噴火が起きた、テレビを見なさい」と担任が興奮気味に教室に飛び込んでくると叫ぶように言った。強烈なスマホゲームの毎 日に恐怖心がマヒしているのか、生徒達ほぼ誰もが担任の驚きにさほど関心は示さなかった。 少年は違っていた。自然現象とゲームソフトの世界は明らかに異次元と覚えていた。 「みんな見ろよ!あの噴火は只者ではないぞ」 「煙の角が3本出ている、すさまじいな」 「へ〜、どこの火山なの」 日本列島も生きている、僕らと同じように。と少年は思うのだった。そして地球は生きている!と誰でも言っていたことが真実を帯びてきた、と 感じた。つい数年前には大きな地震が津波を発生させて東北の一部を壊滅していたばかりだった。怖いけどそれが事実なのだ。 その日の作文の時間に、少年は「怖いし、寂しいし、どうしたらいいかわからない」と書いただけの原稿用紙を提出したのだった。後日、担任 と校長先生が大げさにいじめ?といいながら少年に面談に来たものだった。もちろん少年は「いえ、違います」と深刻そうに言ったあと、「馬鹿な 大人たち」とつぶやき、にたりと笑った、後ろ向きで。 了(27・11・10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■「余生充実?」(24・11・19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
こたつに入ってミカンでも食べていたら?なんて最近誰かに言われて、むっとしているところだった。今からでも一花咲かせられるかとうっ すらと考えているところだっただけに男はことに不愉快になった。 74歳になる高名な演奏家が、いまだに的確な自分の奏法を模索しているという話をラジオで聞いたし、同じ70歳代の女性が文学賞受賞 ニュースをテレビで見たばかりだった。 「まだ10年は現役だ」つぶやきだけは気合が入る。シニアがあちこちで新たな活躍ぶり、嬉しい限りと考える68歳の爺さんだった。 「希望の星が、あちこち瞬いているぞ。嗤われたって構うものか」 爺さんは台所仕事をしているかみさんをしり目に玄関に立った。 「どこ行くの?もうじきお昼なのに」 同い年のかみさん、怪訝そうに言った。 「ウォーキングだ。宇宙開闢以来、人は歩くようにデザインされているんだ。いつまでも現役でな」 年金を人並みにもらえて、とにかく切り詰めれば生活はできていた。マスコミや医師などからの指南で、歩くことを日課にし始めたばかり だった。いつまで続くかしらと、女房の声を背にして出かける。 「死ぬまで続けばいいわけだ。大した時間じゃない」 首に巻いたタオルが、風に揺れた。まだこたつに入る季節ではなかったが、風は冷たかった。陽だまりでは汗ばむといったところだ。 玄関を出ると隣の猫が急に足元を横切る。 「どうした。ネズミでも出たか」 よろけはしたが、そのくらいでは転ぶはずもなかった。だが何か変な予感がした。男は新しい挑戦をぼんやりと考えていたが、斑猫の目 が、朝の光を不気味に反射していた。 俳句、短歌、あるいは近所の役にでも立つ自治会関係?統一性はなかったが、部屋にいるだけはさみしかった。 汗ばんでくる体を感じながらいつものコースをかえて、商店街の裏側に入る。何か若いエネルギーのある世代と接触があればいいが、と ぼんやりと過ぎていく風に思いを託すか。 風と一緒に爺さんは何かが横切るのを感じた。猫ではない、自転車だ。若者のエネルギー、轟音が聞こえるほどに目の前を横切って行っ た。「ぼんやり歩くな」の罵声にやられたように爺さんは路面にたたきつけられた。定番の携帯電話しながらの自転車だった。 「こら、待て!」 叫びながら精いっぱいの力を込めて立ち上がろうとした。「歩道を自転車で、しかもながら運転…」 何人か目の通りすがりの人が、声をかけてくれたときには、すでに失神していたのだった。 気がついたときは救急病院のベッドの上であった。 「いい加減にウォーキングには注意してもらわなければ」 駆けつけたかみさんが声をかける。看護婦も笑っていた。夕方の窓越しの景色は風に揺れていた。 だから言ったでしょ、無理をしないでよ。の妻の声と一緒にベッドの上で男は「まったく!」と呟くのだった。(了)25・9・13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||